日本において「信教の自由」は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、決して侵害されるべきではない。
しかし、現在の日本の状況はどうなっているのか?
日本政府は、2023年10月に家庭連合(旧統一教会)に対して解散命令の請求を行った。だが、これは様々な理由から国による「信教の自由の侵害」にほかならない。特定の宗教団体が解散に追い込まれようとしていることは、国家権力による宗教迫害とも言えるのではないか?
では、そもそも「信教の自由」はなぜ守られなければならないのか?
もし家庭連合(統一教会)が解散命令を受けた場合、日本社会にどのような影響があるのか? そして、マスコミが決して報じない真実とは何なのか?
この記事では、これらの疑問を掘り下げていく。
信教の自由とは?何故守られないといけないのか
個人の尊厳と社会の多様性を保証する重要な人権
信教の自由は、個人の尊厳と社会の多様性を保障する重要な人権の一つだ。どのような宗教や信仰であれ、次にあげる理由から社会で守られるべきものとされている。
- 基本的人権の一部である
信教の自由は、思想・良心の自由とともに、個人が自由に生きるための基本的人権だ。これが制限されると、人間の内面的な自由そのものが脅かされることになる。 - 個人の信念を尊重するため
宗教は多くの人にとって人生の指針となるもの。それぞれが持つ信念や価値観を自由に表明し、実践できることは、人間の尊厳を守るために不可欠だ。 - 思想・表現の自由と密接に関係している
信仰の自由が制限されると、思想・表現の自由も抑圧される可能性が高くなる。社会が画一的な価値観に支配されることになれば、多様な考え方や議論が制限され、民主主義の根幹が揺らいでしまう、 - 歴史的に弾圧が大きな悲劇を生んできた
過去の歴史では、宗教的迫害が戦争や虐◯、社会的混乱を引き起こしてきました。例えば、ヨーロッパの宗教戦争や、日本でも戦時中の国家神道の強制など、信仰の自由が奪われた時代には深刻な人権侵害が起きている。 - 社会の平和と多様性を維持するため
信教の自由が保障されることで、異なる宗教や価値観を持つ人々が共存できる社会が築かれるもの。特定の宗教が強制されたり、弾圧されたりすると、対立や分断が生じ、社会の安定が損なわれてしまう。 - 国家と宗教の分離(政教分離)の原則を守るため
国家が特定の宗教を優遇したり、逆に弾圧したりすると、政治が宗教によって左右され、不公平な社会になってしまう。政教分離を保ち、公平な社会を実現するためにも、信教の自由は守られるべきだ。
信教の自由は何故守られなければならないのか
「信教の自由」は、個人が自由に宗教を信じる、あるいは信じない権利を保障する基本的人権の一つ。これは日本国憲法第20条でも明記されており、国家が特定の宗教に干渉したり、弾圧したりすることを禁じている。
第20条(信教の自由)
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
- 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本が戦後、民主主義国家として発展する上で、「信教の自由」は国民の思想・信仰の権利を守る大切な柱だった。
歴史を振り返ると、特定の宗教が弾圧されたことで社会全体が不安定になったり、人権が侵害された例は世界中に多くある。そのため、国家が宗教に介入することは極めて慎重でなければならない。
しかし、現在の日本では、統一教会(世界平和統一家庭連合)に対する政府の対応が、信教の自由を侵害しているのではないかという強い懸念があり、世界中で問題視されている。
とりわけ、2022年8月末に岸田政権下で行われた、自民党による「統一教会との関係断絶宣言」は、その後の宗教団体や信者に対する社会的な差別や迫害を助長する結果となっている。
統一教会が解散命令されればどうなる?信教の自由は?
政府の「宗教弾圧」としての側面
家庭連合(統一教会)に対する解散命令請求の具体的動きは、岸田文雄前首相がこれまでの法の原則を変え、「刑事事件のみならず民事訴訟も解散命令請求の理由に含める」との見解を国会の場で示したことから始まった。これが2022年10月19日のことだ。
これまでの日本の法制度では、宗教法人が解散命令の対象となるのは重大な刑事事件を起こした場合に限られていた。しかし、統一教会に対しては刑事事件の立件が一切ないにもかかわらず、日本政府は、7回にも及ぶ文科省による質問権行使をはじめ、強引に解散命令請求へと進めてきた。
さらに、いわゆる「被害者」とされている人の多くは、統一教会信者の脱会活動を行う基督教の牧師や脱会屋と言われる人達による拉致監禁の被害を受けた元信者であり、彼らの証言は脱会屋の指示等から「被害額」を誇張しているケースが少なくない。
日本政府は、こうした特殊な背景を無視し、「被害の実態」を調査すると言いながらも、統一教会反対派の弁護士や元信者の話は聞いても、現役信者の意見には一切耳を傾けていない。
このように、一方的に統一教会を「社会的悪」と決めつける政府の対応は、憲法違反の可能性が大きいと言わざるを得ない。
マスコミの偏向報道の影響
統一教会をめぐるマスコミの報道は、ほとんどが元信者や反統一教会活動家の意見に偏っており、現役信者の声はほぼ取り上げられていない。
反統一教会活動家とは、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の弁護士や、自称「統一教会問題に詳しい」ジャーナリスト・学者などを指す(名前はあえて出さない)。
しかし、彼らの主張には明らかな誇張や印象操作が含まれている場合が多く、時には単なる憶測や事実に基づかない情報も含まれている。それにもかかわらず、マスコミはそうした偏った意見を一方的に報じ続けている。
こうした報道姿勢は、世間の偏見や誤解を助長し、信者への差別や社会的迫害を加速させる大きな要因となっている。
統一教会の解散命令がもたらす社会的な影響
法人格の喪失と宗教活動の制限
統一教会が宗教法人格を失うことで、税制優遇措置がなくなり、全国各地にある統一教会の資産が整理・処分されることになる。
これは何を意味するか?というと、単に宗教法人としての優遇措置が無くなるといったことではなく、信仰上拠り所ともなる「礼拝施設」が無くなることも意味する。また資産が整理されることにより、教会の運営が著しく困難になるケースも考えられるだろう。
事実上、宗教活動の自由を奪うことにつながるのだ。
家庭連合職員の全解雇の影響
解散命令が下されれば、家庭連合(統一教会)の職員は全員解雇され職を失う。一斉にだ!
職員の年齢層は地域によっても全く違うが、比較的年齢層が高い人が多く再就職も容易でないだろう。多くの信者の家庭が経済的な困難に直面する事態を引き起こすことも考えられる。
信者への社会的差別と迫害の激化
自民党が家庭連合(統一教会)との関係断絶を宣言して以来、信者に対する社会的差別は、次の事例にもあるように、すでに無視できないほど深刻な状況となっている。
- 公共施設の利用制限:統一教会がイベントを開催しようとしても、会場を借りることが困難になった。
- ボランティア活動の妨害:統一教会信者による地域貢献活動も、偏見によって制限されるようになった。
- 医療機関での診察拒否:信者であることを理由に、一部の病院で診察を拒否されるケースが報告されている。
- 教育現場での差別:高校や大学で、教師が統一教会信者の生徒に対し、心ない差別的な発言をする事例が増えている。
- 信者の精神的苦痛:マスコミや世間の批判によって、特に二世信者の間でうつ病などの精神疾患を患うケースが増加している。
政府与党(自民党)が一宗教団体と関係を断つという決定は、単なる一政党の主張とは異なり、社会全体に与える影響が極めて大きい。これは、マスコミや共産党などの野党が発する批判とは全く次元の違う問題であり、信者にとってみれば、とてつもなく重大な意味を持つ。
解散命令が司法から下された後も宗教団体としての活動は可能だ。しかし信者を取り巻く差別的な状況が今よりもさらに悪化するのは火を見るより明らかだ。
地方の各自治体も、国の決定を免罪符とし、統一教会との関係を完全に断絶しようとするだろう。その結果、信者たちは日本社会の中でまともに生活することができるのか?家庭連合の信者たちは、まるで「隠れキリシタン」のように、自らの信仰を隠しながら生きることを余儀なくされるかもしれない。
マスコミや反統一教会派が良く言う、「解散命令になっても、法人格の剥奪で税制優遇措置が無くなるだけ。統一教会信者は今ままで通り信仰を続けられる」という主張は、今の日本の状況を考えたときには、そんな甘いものではなく、本質的に全く違うと言わざるを得ない。
他人事とは言え、「今ままで通り大丈夫」などと、良く言えたものだ。

日本は信教の自由とどう向き合うべきか?
日本政府が行った家庭連合(統一教会)への解散命令請求は、日本が本当に信教の自由を尊重する国なのか?を問う非常に重要な出来事だ。それを理解している人が一体どれほどいるのか。
「信教の自由」問題についての日本の置かれた課題
- 信教の自由の厳格な保障
国家が特定の宗教を政局的な判断で弾圧することは、憲法に違反する行為であり、将来的に他の宗教団体にも同様の圧力が加えられる危険性を生み出す。
さらに、このような国家権力の介入は宗教団体にとどまらず、やがては他のあらゆる団体や個人の自由にも影響を及ぼす可能性がある。これは統一教会(家庭連合)だけの問題ではなく、日本の民主主義そのものが危機に瀕していると言えるだろう。 - 拉致監禁問題の再調査
いわゆる「被害者」とされる人々の証言の信憑性を改めて検証し、統一教会反対派のキリスト教牧師や脱会屋による拉致・監禁による棄教強要の実態を明らかにする必要がある。
これは、信仰を持つ人々の基本的人権を守るうえで極めて重要であり、決して無視されるべき問題ではない。 - 宗教への公正な対応
家庭連合(統一教会)は刑事事件を起こしていない。それにもかかわらず、政府が統一教会だけを規制の対象とするのは、明らかに不公平な対応だ。政府は、他の宗教団体とも公平性を確保し、一宗教を特別に敵視するのではなく、公正な立場で対応すべきだ。
特定の宗教を標的にするような政府の姿勢は、社会の分断を生み出し、将来的にさらなる混乱を引き起こす危険性がある。
日本は「信教の自由」を守る国であり続けることができるのか
「信教の自由」は、民主主義社会の根幹を支える重要な権利だ。
しかし、日本政府による統一教会(現・家庭連合)への解散命令請求は、国家による宗教弾圧とも捉えられかねない重大な問題を含んでいる。

特に、統一教会(現家庭連合)に対して刑事事件の立件がないにもかかわらず、政府が「被害」を拡大解釈し、元信者やその家族たちの偏った意見のみを鵜呑みにして一方的に解散命令請求を行っている現状は、憲法違反の可能性すらあると言える。
さらに、もし司法が解散命令を認めて施行した場合、教会の職員は全員職を失い、全ての信者たちは今よりさらに強い社会的迫害に直面するのは明らかだ。
信仰を理由に職を奪われ、社会から排斥される——まるで「隠れキリシタン」のように信仰を隠して生きざるを得なくなるかもしれない。いや、その可能性は極めて高いと言わざるを得ない。
与党自民党として統一教会との関係断絶を進め、政局・保身のために解散命令請求に踏み切った「岸田文雄氏」は既に総理大臣の座を退いた。
しかし、今後、総理大臣が誰になろうと、あるいは政権交代が起こったとしても、日本政府が特定の宗教団体に対して下した関係断絶・解散命令請求の決定の影響は長期にわたって残り続ける。この決定により、日本政府は信教の自由に関する責任を問われることになるだろう
むしろ、統一教会に対して行った解散命令請求の措置は将来的に「内面の自由」そのものを脅かす危険性をはらんでおり、決して軽視できる問題ではない。
この状況を前にして、日本は本当に「信教の自由」を守る国であり続けることができるのか。今こそ、原理原則に立ち返り、真剣に考えるべき時ではないか。
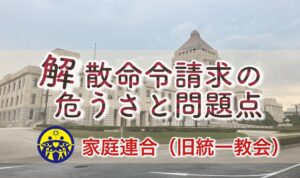



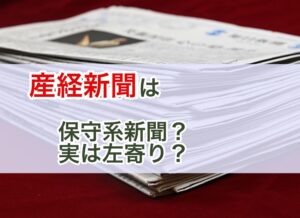





コメント