日本政府・文部科学省は、統一教会(現:世界平和統一家庭連合)への解散命令請求を東京地裁に行ったが、これが社会的関心を大きく集めている。
政府は前例に無い「民事的違法行為」も判断の根拠にした上で、7回もの質問権行使を行い、結果として2023年10月13日に解散請求へと踏み切った。
前・岸田政権は世論の圧力やメディアの報道を背景に、政治的パフォーマンスともとれる対応を進めたが、この措置が明らかに法治国家として正当な判断とは言えないだろう。信教の自由という憲法の根幹に関わる上で大問題だ。
宗教法人の解散は単なる行政処分ではない。それは信者一人ひとりの精神的自由、思想の多様性、そして民主主義の基盤に関わる重大な判断である。
本記事では、統一教会(現:家庭連合)への解散命令請求をめぐる問題点を多角的に検証し、その危うさと社会的影響の問題点について考察する。
2025年3月25日、東京地方裁判所で統一教会(現:家庭連合)に対する解散命令の判決が下されてしまった。しかし、この一審の結果をきっかけに、国の対応がいかに異常で不自然なものであるかが次々と明らかになっており、多くの有識者からも疑問の声が上がっている。この点については、別の記事で詳しく取り上げる予定だ。この記事にも解散命令請求の問題点について多く書いているように、常識的に考えても次の高裁(控訴審)では逆転勝訴する可能性が高い。
統一教会への解散命令請求の問題点について
信教の自由の侵害になる
日本国憲法第20条は、信教の自由を基本的人権の一つとして明確に保障している。
第20条(信教の自由)
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
- 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
この条文は、個人が自由に信仰を持ち、宗教的実践を行うことに対して、国家が干渉することを原則として禁じている。にもかかわらず、文部科学省による統一教会への解散命令請求は、この信教の自由に対する重大な侵害だ。
たとえ、その宗教団体の何らかの活動が社会的に批判されていたとしても、国家が信仰の内容や教義、信者の思想信条に関与することは、憲法上極めて慎重に扱うべきものである。
宗教的マイノリティや、(ある一部の人から見て)異端とされる信仰が、国家によって排除される流れが正当化されれば、日本社会における信教の自由の土台そのものが大きく揺らぎかねない。
証拠の不透明さと根拠の薄弱さ
統一教会に対する解散命令請求の根拠として、文部科学省は以下の存在を挙げている。
- 「法令に違反する行為」
- 「著しく公益を害する行為」
しかし、その具体的な証拠や事実関係については、明確な詳細が明かされておらず不透明だ。
一宗教法人の解散命令という非常に重大な措置においては、裁判所の確定判決や刑事罰など、明確かつ客観的な違法性の証明が本来必要であるはずだが、現時点で提出された根拠の多くは、相談件数や苦情といった定性的な情報にとどまっている。そもそも統一教会(現・家庭連合)には、これまで刑事事件は無い。
また、これらのデータや元信者の陳述等が正確かつ中立的に集計されたものであるかについても非常に大きな疑問が残る。実際のところ、文科省は陳述書の捏造というあるまじき不正を行っていたことが後に発覚したからだ。

統一教会(現:家庭連合)に対する批判的な報道や世論の高まりが、文科省による証拠の評価に影響を及ぼしている可能性は高い。根拠が曖昧なまま、一宗教法人の解散を進めることは、法の支配に基づく判断とは言い難く、他の団体にも同様の不当な扱いが波及する危険性を孕んでいる。
手続きの非公開性と公正さの欠如

統一教会(現:家庭連合)への解散命令請求における審理は、その過程が非公開で進められており、極めて透明性に欠けている。このような重大な行政措置が、国民や関係者に詳細を開示せずに進行することは、法治国家としての原則に反する。
特に問題なのは、統一教会側に十分な反論機会が与えられているかどうかが不明な点である。一方的な主張や報告をもとに手続きが進められているとすれば、それは公平性を著しく欠いた行政判断だ。
さらに、情報公開が限定されているため、国民が事実に基づいた判断を下すことも難しい。解散命令が信教の自由や基本的人権に直結する問題である以上、その手続きは最大限に公正かつ公開性の高いものでなければならない。
現状では、「すでに結論ありき」の印象を拭えず、国家権力による恣意的な処分であるとの疑念を深める要因となっている。

岸田政権による保身ありきの政局的判断
統一教会(現:家庭連合)への解散命令請求の背景には、岸田政権による政局的、つまり自身の保身を最優先とした政治判断が色濃く見て取れる。これこそが、今回の件で最も深刻な問題である。
本来、宗教法人の存続に関わる判断は、法と証拠に基づいて慎重に行われるべきものだ。しかし今回の請求は、そうした原則を無視して、政治的な都合を優先して進められた疑いが強い。
その発端となったのは、2022年7月の安倍元首相の事件後に噴出した、自民党と統一教会の関係を巡る問題である。本来、政教分離の原則に照らしても、それ自体に何も問題はなかったはずだ。
ところが、マスコミが「癒着」「接点」などと騒ぎ立て、一部の“統一教会に詳しい”とされる人物たち――たとえば鈴木エイト氏や紀藤正樹氏など――が、事実に誇張や虚偽を巧みにに交えて批判を連日繰り返した。
この流れに乗じて、野党の政治家たちも自民党を激しく追及し、世論もそれに同調して熱狂的に巻き込まれていった。
本来、自民党と統一教会の関係は、他の宗教団体との関係と何ら変わるものではなく、特段問題視されるべきものではなかった。しかし、岸田政権はこの批判を正面からはねのけることもできず、2022年8月末には統一教会との関係断絶を宣言する事態にまで至った。
それでもなお批判の矛先は止まず、政権はさらなる“防衛策”として、近年ではトラブル件数も減っていて刑事事件などは1件もない統一教会に対して、過去の民事トラブルを誇張し、「悪」として描き出す戦略に出た。その延長線上にあるのが、今回の解散命令請求であり、まさに世論に迎合する姿勢の象徴といえる。
要するに、政権与党が自らへの批判をかわすために、統一教会という宗教団体を“スケープゴート”にした構図が浮かび上がってくるのだ。
これは政治の責任転嫁であり、健全な国家運営とは到底言えない。
他の宗教団体への波及するリスク

統一教会(現:家庭連合)に対する解散命令請求が前例として確立すれば、他の宗教団体に対する同様の措置が容易に行われる危険性がある点は、見過ごすことができない。
特に、「社会的に問題視されている活動」や「信者とその家族間のトラブル」といった曖昧な基準が今回の請求理由に含まれていることは、極めて憂慮すべき事態だ。
このような曖昧な基準が一度でも前例として認められれば、今後は新興宗教やマイノリティ宗教、さらには政権と異なる価値観を持つあらゆる団体までもが、恣意的な理由で狙い撃ちされるおそれがある。
つまり、宗教団体の「社会的評価」に基づいて国家がその存続を左右するような事態が常態化すれば、日本社会における宗教の多様性と自由は根底から脅かされることになる。
このような波及的影響を考慮せずに解散命令を進めることは、宗教政策のあり方を大きく誤ることに繋がると言わざるを得ない。
「悪質性・組織性・継続性」の三要素は当てはまらない
宗教法人法第81条1項1条には、解散命令の要件として「法令に違反して著しく公益を害する行為」を定めている。しかし、この「著しく公益を害する」という文言は極めて抽象的であり、その運用には本来、厳格かつ客観的な基準が求められる。
文部科学省は、岸田首相の発言を受けて「悪質性」「組織性」「継続性」という三つの要素をもってから統一教会の解散命令の要件としてきた。
しかし家庭連合の実態を見れば、悪質性・組織性・継続性のいずれも成立していないといえるが、特に「継続性」については決定的に誤っている。
統一教会は2009年に公式に「コンプライアンス宣言」を発表し、信者への指導方針や献金の取り扱い、伝道活動などに関して内部ルールを徹底して見直してきた。それ以降、民事トラブルや苦情件数は明らかに激減しており、少なくとも制度的・継続的な違法行為が行われていたとは言えない。組織としても、コンプライアンスを見直し、再発防止策を継続的に実施してきた。
過去に様々に問題があったことは謙虚に受け止める必要があるが、現在までの15年近くにわたって改善を続けてきた事実(それは数字にも表れている)を無視して「継続性がある」とするのは、きわめて不合理かつ不公正な判断である。
むしろその姿勢は「悪質性」の否定材料でもあるといえる。こうした状況を正確に把握せず、過去の一部の問題だけを根拠に処分を下すことは、客観性と法的妥当性を欠いた極めて恣意的な行政判断である。
重大事件の犯人に迎合する危うさ
統一教会(現:家庭連合)をめぐる問題が社会問題化した直接の契機は、2022年7月の安倍晋三元首相暗殺事件である。
だが、事件を起こした犯人の供述に基づいて、マスコミが統一教会に関する問題を過剰に報道し、野党が追及し、世論が紛糾した結果、政府が宗教法人の解散命令請求に踏み切ったという流れは、極めて危うい前例をつくることになる。
犯人が供述した「母親が統一教会に献金したことで家庭が崩壊した」という主張は、それが事実だとしても、なぜ安倍元首相を狙うに至ったのかという動機が飛躍していて、どう考えても信憑性が低いと言わざるを得ない。
それにもかかわらず、その供述を前提に社会全体が動き、1つの宗教団体を国家権力によって解散に追い込むという事態に至ったことは、事実上、重大事件の犯罪者の意図に社会が迎合したことを意味する。
これは、法治国家としてあってはならないことであり、今後も同様の手法が模倣される可能性を考慮すれば、民主主義社会にとって深刻な脅威となる。暴力や犯罪行為を通じて社会が動かされるような前例を、決して容認してはならない。
メディアと政府の過剰な連携

統一教会(現:家庭連合)をめぐる一連の騒動では、メディア報道と政府の動きが不自然なまでに連動している印象が否めない。
とりわけ、統一教会に関する否定的な報道が連日繰り返され、それに呼応するかのように政府が解散命令請求を打ち出すという流れは、冷静な政策判断というよりも、感情的な世論に押し流された拙速な対応と映る。
もちろん、報道機関が社会問題を取り上げる役割を果たすことは重要だが、それが一方向の視点や断片的な証言ばかりに基づいて過熱し、政府の政策判断を誘導するような結果を招くのは、健全な民主主義にとって危機的な状況だ。
情報が整理される前に世論が先行し、それに迎合するかたちで国家権力が動くのであれば、本来あるべき「法と手続きに基づく慎重な判断」は形骸化してしまう。報道と政治の距離感が適切に保たれなければ、今後も感情に流された政策決定が繰り返されるおそれがある。
統一教会だけ狙い撃ちしている
統一教会(現・家庭連合)に対する解散命令請求は、類似の問題を抱える他の宗教団体には適用されていないという点からも、極めて不公平な対応と言わざるを得ない。
たとえば、高額な献金の要求や信者の家庭に深刻な影響を及ぼす活動は、他の宗教団体や宗教的性格を持つ組織でも確認されているが、そうした団体には「解散命令」が一切出されていない。
実際に、これまでに宗教法人法第81条に基づいて解散命令が請求されたのは、オウム真理教(アレフの前身)と明覚寺のわずか2件のみである。とりわけオウム真理教に至っては、社会的に重大な刑事犯罪を組織的に実行し、多数の死傷者を出したという極めて重大な事実があった。
一方、統一教会(現:家庭連合)はどうか?
刑事事件として立件された組織的違法行為は存在しておらず、個別の民事トラブルばかりである。それも数十年前等のかなり以前のものがほとんどだ。
また、他の宗教法人の中には、信者への暴行・脅迫、あるいは死亡事故まで起こしているにもかかわらず解散命令が請求されていない宗教法人もいくつか存在する。いずれの団体も今も法人格を維持している。
このように、より重大な問題を抱える団体が行政処分の対象とされない中で、統一教会のみが強制的な解散請求を受けるという現状は、国家が特定の宗教団体を選別し、狙い撃ちしているという印象を否応なく強めるものである。
一貫した基準なく一団体にのみ厳罰を科すことは、法の下の平等という原則に反し、宗教行政における公平性を著しく損なう結果となる。
こうした措置が仮に正当化されれば、「政権や世論にとって都合の悪い宗教団体は排除され得る」という極めて危険な前例となり、日本社会における信教の自由と宗教的多様性に深刻な影響を与えることは避けられない。
反共産主義の立場ゆえの標的化
統一教会(現・家庭連合)が長年にわたり反共産主義を明確に掲げてきたことが、今回の解散命令請求において不当に標的とされる一因になっている側面も大きい。
冷戦期以来、統一教会は一貫して反共の立場を取り、日本国内でも共産主義に対する明確な思想的対抗軸を持って活動してきた。このような思想信条自体は、憲法が保障する思想・信教の自由に属するものであるが、現実には、統一教会の反共的性格が、左派的思想を持つ政治勢力や組織団体にとって「排除すべき対象」とされているように見える。
日本共産党は、これまでも様々な局面で統一教会を敵対視してきた。日本共産党の前委員長の志位和夫氏は、2022年10月に「共産党からすれば統一教会との最終戦争だ」とも言っている。
田原さん「共産党からすれば統一教会との最終戦争だ」。
志位「長い闘いだった。彼らが反共の先兵として最初に牙を剥いたのは1978年の京都府知事選だった。2000年の衆院選では膨大な規模の反共・謀略ビラがまかれた。今度は決着つけるまでとことんやりますよ」https://t.co/k1i5qNS8ZQ— 志位和夫 (@shiikazuo) October 26, 2022
また「全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)」等の左派系の弁護士団体なども、積極的に統一教会(家庭連合)を批判し、国による解散命令を求めてきた背景にも、政治的思想の対立構造もある。

日本共産党をはじめとした野党が強靭に政府与党に統一教会問題の追求してきたのはそうした背景が間違いなくあるが、結果的に岸田政権はその追求に負けてしまったと言わざるを得ない。
かつて中曽根首相が、国会で共産党議員に統一教会との関係を断てと言われ、毅然と突き返したのとは月とスッポンだ。

まさに一宗教団体を「都合が悪い」という理由で排除するような国家運営は、自由と多様性を重んじる社会において極めて危険な流れと言わざるを得ない。
国際的に見た日本の宗教迫害
統一教会(現:家庭連合)への解散命令請求は、国内の宗教行政にとどまらず、国際的な人権基準との整合性という重大な問題を孕んでいる。
日本は国際人権規約(自由権規約)を批准しており、信教の自由を保障する国際的責任を負っている。その中で、特定の宗教団体に対して国家が解散を命じることは、国際社会から「宗教弾圧」と受け止められる危険性が高い。
その中で、国際人権B規約20条2項では以下の通り謳っている。
2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
(引用:国際人権B規約20条2項)
特に注目すべきは、アメリカを中心とした信教の自由擁護の動きである。
米国では、2025年1月に誕生した共和党トランプ政権下で宗教の自由が外交政策の中核に据えられ、ホワイトハウスに「信仰局(Faith and Opportunity Initiative)」まで設置された。
この信仰局の初代局長を務めているポーラ・ホワイト牧師は、日本政府の統一教会への対応について、以前から「宗教的迫害にあたる」として明確に懸念を表明している。
最近では、2024年12月8日に東京で行われたICRF(国際宗教自由連合)2025の大会の場で、以下の力強いビデオメッセージを寄せている。
ここで語られている内容をピックアップすると、以下の通りだ。
- トランプ大統領は宗教の自由の非常に強力な支持者であり、あらゆる信仰とあらゆる人々の宗教の自由に対する、揺るぎない支持を強めていく
- 日本は、宗教の自由に関する公約を守っていないと考える世界中の著名な指導者たちから懸念の声が上がっている
- 米国国務省の報告では、安倍元首相の暗殺以降、日本統一教会が日本における不寛容、差別、迫害のキャンペーンの犠牲者になっている
- 岸田首相、外務大臣、裁判所に宛てて、米国の現職下院議員、前職国家元首たち、元米国国務長官、元米国下院議長らが書簡を送った(しかし返事はない)
- 偉大な同盟国である日本に対し、すべての人々の宗教の自由を守るよう強く求める。
米国はこれまでも、様々な組織や国会議員等が日本政府に忠告してきたが、岸田政権は全て無視した。日本政府は宗教弾圧を行っている自覚があるからだろうか。
また、米国務省でも、「信仰の自由に関する国際報告書」において、日本での統一教会とエホバの証人に対する日本の対応は見過ごせないレベルと批判しており、信仰の自由の重要性を強調している。
このような世界からの声は、宗教の自由が国際社会においていかに重視されているかを物語っている。日本がこの問題を軽視したまま対応を誤れば、人権国家としての評価を大きく損ね、外交面にも深刻な影響を及ぼしかねない。
解散命令請求の要件に民事まで含めてきた
統一教会(現:家庭連合)に対する解散命令請求には、そもそも民事と刑事という法的性質の異なる問題を一緒にしているという重大な問題がある。
背景には、2022年10月19日、岸田前首相が前日の国会答弁を撤回し、「民事上の違法行為も解散命令の対象になり得る」と明言したことがある。これは従来の政府見解、すなわち刑事罰や重大な組織的犯罪がなければ解散請求は困難であるという立場を大きく覆す発言であった。
自民党総裁である岸田首相のこの方針転換により、統一教会に関しては刑事事件ではなく、高額献金をめぐる民事トラブルや家庭内の問題といった個別の事案が、組織の「違法性」として扱われるようになった。
しかし、民事トラブルは本来、当事者間での和解や損害賠償を通じて解決されるべきであり、それを理由に宗教法人そのものを解散対象とすることには、明らかな法的飛躍がある。
民事と刑事の線引きを曖昧にしたまま、世論や政治的圧力を背景に新たな「解釈変更」を持ち出す手法は、法治国家の原則に反するものであり、他の宗教団体や民間組織にも悪影響を及ぼす前例となる可能性がある。
宗教活動と社会活動の区別の曖昧さ

統一教会(現:家庭連合)に対する解散命令請求の背景には、宗教活動と社会活動、特に政治的関与との区別が意図的に曖昧にされているという問題がある。
宗教団体が社会的な活動を行ったり、特定の理念に基づいて政治的な発言や関与を行ったりすること自体は、憲法が保障する信教の自由および表現の自由の範囲内で認められている。実際、日本国内の多くの宗教団体が平和活動や政治的発言を行ってきた歴史がある。
ところが統一教会に関しては、その政治的関係性や理念表明が「違法性」の文脈で扱われており、あたかも政治的発言を行う宗教団体は排除されるべきかのような印象が形成されている。これは、宗教団体が社会に関与する自由を根本から否定するものであり、宗教を公的空間から追い出そうとする動きにもつながりかねない。
宗教と社会の関わりは本来切り離せないものであり、宗教法人であることを理由に社会的発言や関与を制限するのは、信教の自由に対する重大な制約となる。宗教活動と社会活動の区別を恣意的に運用すれば、多様な思想や信仰が健全に共存する社会の基盤が崩れることになろう。
「公益を害する」の定義が極めて曖昧
統一教会(現:家庭連合)への解散命令請求において、文部科学省は宗教法人法第81条第一項を根拠に「著しく公益を害する行為」があったと主張している。
しかし、この「公益」という言葉は極めて抽象的かつ相対的であり、具体的に何をもって「公益を害する」とするのか、明確な基準が存在しない。時代や社会情勢、政権の価値観によっても判断が左右されうる以上、このような曖昧な概念をもとに宗教団体の存続を左右するのは、極めて危険な運用と言わざるを得ない。
たとえば、特定の宗教教義が一部の国民感情やメディアの価値観と合致しない場合、それだけで「公益を害している」とみなされることがあれば、宗教的少数派の存在そのものが否定されかねない。今回、統一教会が「社会的に問題視されている」という空気のもとで、公益性が損なわれたと一方的に断じられる構図は、まさに恣意的判断の典型である。
本来、公益とは多元的で、価値観の多様性を前提とすべき概念である。その公益を政府が一方的に定義し、それを根拠に宗教団体を排除することは、法治国家の理念にも、民主主義社会の根幹にも反する危うさを孕んでいる。
信者の人権とアイデンティティの軽視

統一教会(現:家庭連合)に対する解散命令請求が進められる中で、最も軽視されているのが、信者一人ひとりの人権と信仰に基づくアイデンティティである。
宗教団体の存続は単なる「法人格」の問題にとどまらず、そこに属する信者たちの精神的なよりどころであり、人生観や価値観、家族関係にまで深く関係している。
そのため、国家が宗教法人の解散を命じることは、信者の人格的尊厳や信教の自由に対する深刻な侵害になり得る。
現実にはすでに、統一教会(家庭連合)の信者たちは世間から偏見や差別の目で見られており、職場や地域社会で差別を受けたり、孤立を感じている人も少なくない。身体的に暴力を振るわれたケースもいくつもある。

この状況の中で、国家による解散命令が下されれば、さらに状況が悪化し、信者に対する社会的なレッテル貼りや排除、誹謗中傷といった差別が一層深刻になる恐れがある。これは、個人の思想・信仰の自由が尊重されるべき民主社会において、決して看過できない問題である。
加えて、公的議論の中では、元信者と言われる方の声は聞いても、現役信者の声は一切無視される。そして「被害者」の側面が強いのに、一括して「加害者」と扱われる風潮も強い。
しかし、家庭連合の信者は、自らの意思、そして自らの良心で信仰を選んできた。マインドコントロールや洗脳等では決してないのだ。
家庭連合(統一教会)の教えに基づいて、人のために生き、自らの人生を築いてきた人々が大勢いる。その信仰や人生の選択を外部から一方的に否定することは、その尊厳を踏みにじる行為でもある。
信仰の自由とは、単に「どの宗教を信じるか」を国家が制限しないということだけではない。「信じ続ける自由」「宗教団体に所属する自由」もまた不可分の権利である。こうした信者の権利を顧みずに制度的な解散が進んでしまえば、日本社会における信教の自由は重大な転機を迎えることになるだろう。

法と証拠に基づいた冷静で理性的な議論と判断が必要

統一教会(現・世界平和統一家庭連合)への解散命令請求について、日本政府や文部科学省は「社会的正義」や「被害者救済」を掲げて正当化しているが、それは本質を見誤っている。
その背後にあるのは、岸田政権による政局的な判断、民事と刑事の混同、メディアと政府の過剰な連携、そして何よりも信教の自由や信者の人権に対する深刻な軽視である。加えて、「公益」や「違法性」といった曖昧な基準が恣意的に使われることで、他の宗教団体への波及や、国家が思想的に“好ましくない”と見なす信仰への介入を正当化する前例がつくられようとしている。
つまりは国家による宗教弾圧であるということ。
家庭連合(統一教会)にも様々な課題や問題はあり、そのことについては謙虚に受け止めなければならない。だからと言って、日本政府が定義するような「悪質性」「組織性」「継続性」の3拍子揃った社会的問題のある宗教法人として、解散命令させられるほどの悪質な団体なのでは決してない。
これはこの記事全体で様々な観点から伝えてきた通りであり、解散命令請求は明らかに不当であることは何度も強く訴えたいことだ。
今回の日本政府の措置は、家庭連合(旧統一教会)という一団体の問題にとどまらない。日本が信教の自由、多様性、そして民主主義という根本原則を本当に守る意思があるのかが問われる重大な局面である。
家庭連合の存続がどうなるかは最終的に司法判断に委ねられているが、私たち社会全体に求められているのは、空気や感情に流されるのではなく、法と証拠に基づいた冷静で理性的な議論と判断である。
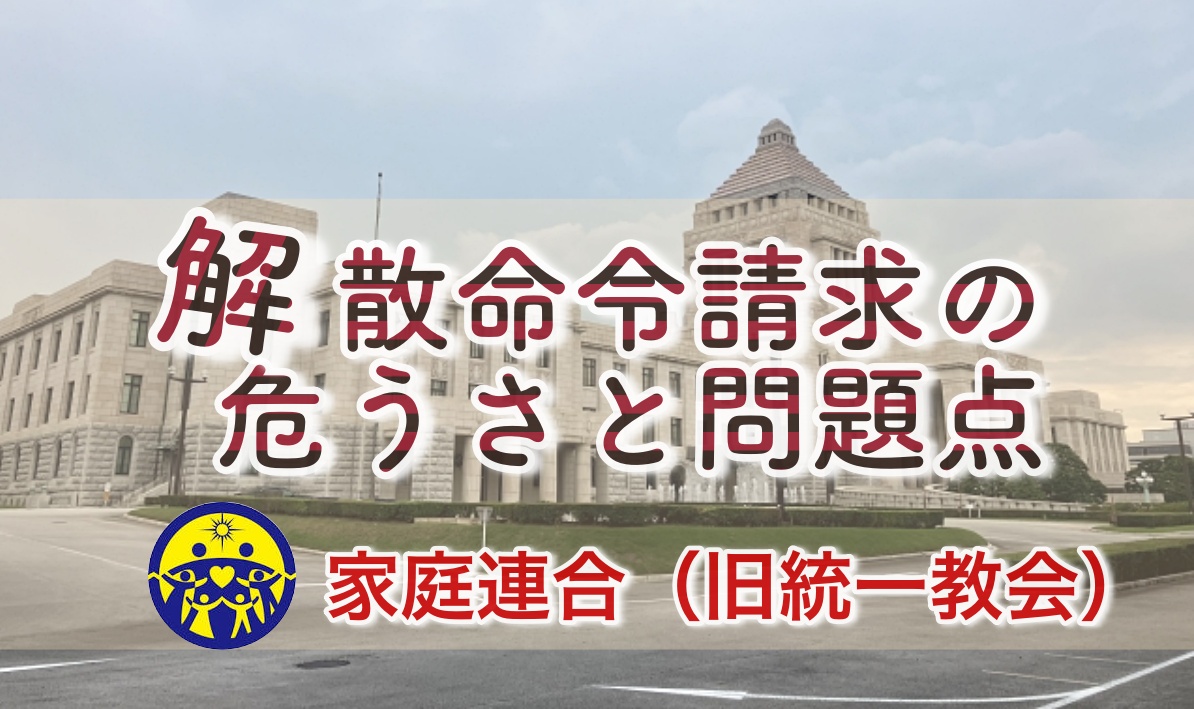
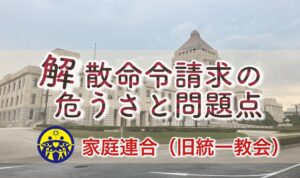

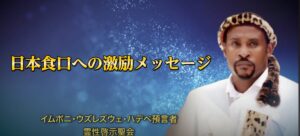


コメント